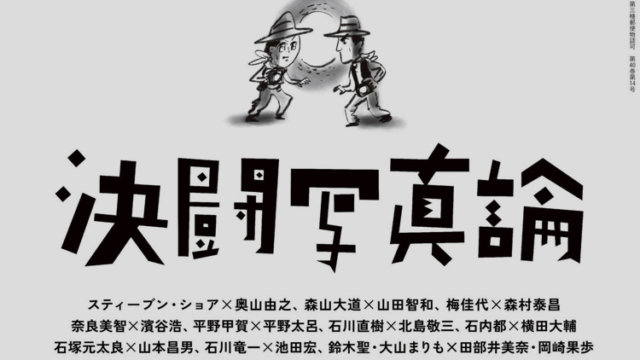FUJIFILM X-Pro3, Nokton 23mm f1.2 SC
FUJIFILM X-Pro3, Nokton 23mm f1.2 SC僕らはいま、おそらく人類史上もっとも写真を撮ったり、見たりして過ごしている。それはスマホカメラでありインターネットの影響で、誰もがもはや意識することのない浸透具合でそういう日常を送っている。
それによってカメラ産業が苦戦を強いられているとも言われるが、僕はそこに可能性も感じている。
昔なら「写真」はみんなのものというより、ある一部の分野だったり、もしくは記念撮影をする時だけのものだったんじゃないかと思う。
 Nikon Zfc
Nikon Zfcけれどいまは違う。「写真」というものの定義にもよるが、とにかくいまは誰もが必ず画像を撮影してSNSやメッセージアプリで送り合ったりしている。つまり、考え方によっては昔よりも誰もが「本格的カメラ」への距離が近くなっているように思うのだ。
過去に何度も書いているテーマではあるけど、毎日なにかしらの写真をスマホカメラで撮ってるなら、それをせっかくだから本格的カメラで撮ってみれば、人生にかなりクリエイティブな要素を持ち込めると思うのだ。
 FUJIFILM X-E4, XF 18/2R
FUJIFILM X-E4, XF 18/2R FUJIFILM X-E4, XF 18/2R
FUJIFILM X-E4, XF 18/2R FUJIFILM X-E3, Color-Skopar 35/2.5 C-type
FUJIFILM X-E3, Color-Skopar 35/2.5 C-type実際、僕もカメラで写真を撮るようになって、大袈裟ではなく人生が相当豊かになったと思う。そうやってじぶんでカメラや写真の構造を理解し始めると、他の人が撮った写真にも俄然目が向き始める。そして、世の中には素晴らしい写真家や写真集があることも知るようになる。
まあ、僕はあいかわらず写真は上手くないけど、写真とその道具であるカメラが好きになれば「撮る」という行為だけで本人はとても日々満たされるし、写真を「見る」という行為も世界の見方をちょっと変えてくれる。
 FUJIFILM X-E3, XF 35mm f1.4 R
FUJIFILM X-E3, XF 35mm f1.4 Rしかも、カメラと写真がいいところは、主目的が他にあっても、そのどれもに脇役として写真は彩りを添えてくれることだ。散歩が趣味ならついでに首からカメラをぶら下げて歩けば季節の移り変わり撮れるし、旅行や行楽に一緒に持ち出せば、さまざまな思い出を写真に焼き付けることができる。実に「いい距離感」のアイテムなのだ。
わが家にはきょう、川島小鳥さんと臼田あさ美さんの写真集「ソウルメイト」が届いたのだけど、仕事の合間にふと数ページ眺めるだけでも、脳みそがとても心地いい状態へとチューニングされるのがわかる。文字のない写真がもたらすイマジネーションのスイッチは、とんでもなくクリエイティブで凄いのだ。
 川島小鳥さんと臼田あさ美さんの写真集「ソウルメイト」
川島小鳥さんと臼田あさ美さんの写真集「ソウルメイト」だから、本格的なカメラを使ったことがない人にこそ、僕は一台のカメラを所有してみることをおすすめする。なにも高価なものじゃなくていいから、カチャカチャとじぶんでいじってシャッターが切れるカメラがいい。そのなにげなく瞬間や構図、露出なんかを考えながらシャッターボタンを押すと、誰にでも目の前の「いま」が撮れる。世界に一枚しかない「いま」だ。
そういう意味では、カメラは大発明だ。スマホカメラももちろん便利だけど、その大発明の目撃者になる意味でも、そのルーツが感じられる本格的カメラ(いわゆる写真専用カメラ)を手にしてみるのはどうだろう。すでに手にしている人なら、そんなカメラが身近にあることの有意義なことを、いろんな方法で周囲の人にそれとなく広めていければ、それはなかなか幸福な事象にも思える。
そんなことを考えながら、僕はきょうもこのブログ「記憶カメラ」を書いている。