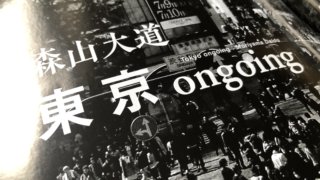Rolleiflex Standard & Kodak Retina type117
Rolleiflex Standard & Kodak Retina type117桜が満開を少し越えた土曜日、二台のカメラにフィルムを詰めて辺りの桜を少し撮り歩いた。
一台は中判の二眼レフ機Rolleiflex Standardと、もう一台は35mm判フィルムカメラKodak Retina type117だ。
共に1930年代のカメラで、製造されて85年ほど経つが、博物館に保管されているならまだしも、こうして今もアマチュア写真愛好家である僕が普通に使えていることに軽い驚きを覚える。
いわゆる電気を使わない「機械式カメラ」だからこその恩恵だ。この世の中で85年もの前のプロダクトが今も普通に使えているモノは、機械式カメラ以外になかなか思いつかない。
電気を一切使わないわけだから、操作も一切じぶんで行わないといけない。感度が固定のフィルムを入れたら、絞りを決めて、シャッタースピードを合わせ、フィルムを巻き上げて、距離をルーペまたは目測で決めたら、シャッターをチャージし、そっとシャッターを切る。
こう書くと数行だが、実際には露出計も使いながらひとつひとつ操作していくんで、一枚撮るのに数分はかかる。デジカメのプログラムモードなら数秒で済ませられる工程だ。
でも、その一枚一枚を数分かけて撮るプロセスが実にいい。それこそ1930年代の人々の時間の流れ方だ。写真とはそういうスピードで撮るものだったはずで、そうすると中判の12枚でもかなりの時間を要するし、36枚のフィルムとなればなかなか撮り終えない。
事実、僕はきょう、Rolleiflex Standardは12枚を撮り終えたが、Kodak Retina type117のほうは15枚ほどしか撮らず、残りのフィルムは明日に持ち越しだ。
フィルムはたしかに値上がりが顕著で数年前のように安価では手に入らなくなった。けれど、たぶん1930年代はもっとフィルムは高価なものだったんじゃないかと思う。そう、その道具であるカメラたちも。
それを考えると、機械式カメラにフィルムを詰めて撮るこの時間の歓びのようなものは、いまは少し割高ではあるもののこうして一般人の僕が体験できるわけだから、意外と幸福な時代を生きているんじゃないかと思う。
少なくとも1930年代の人たちからすると、羨ましがられる環境かもしれない。フィルムが一般人にも使えて、尚且つデジカメも楽しめるハイブリッドな写真時代を体感できているわけだから。
僕は自家現像はしないので、フィルムを現像ラボに出すなら少しまとまった本数の方がいいだろうということもあり、明日用に中判フィルムをもう一本Rolleiflex Standardに装填した。
Retinaの残りフィルムと合わせて、明日はきっとこれでまたお腹いっぱいになれるだろう。そうすると、フィルムもそれほどランニングコストがかかるものでもないとも思える。
これだけ世の中がハイスピードな時代の中で、1930年代の人々の時間の流れ方を体感できることは、とても貴重でちょっとしたタイムマシンのような感激がある。
我ながら、いい趣味に出会えたと思っている。その時間を手にするためのコストとしては、もうしばらくはなんとか工夫してやっていければ小さな幸福である。いや、小さくないな、とても大きく代えの効かない幸福である。