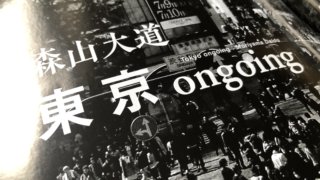Leica IIIa, Elmar 50/3.5
Leica IIIa, Elmar 50/3.5ストリートスナップ・ライカということでいえば、M3よりIIIaだろうな。
僕が本格的に街撮りスナップに目覚めたのは、このバルナック型Leica IIIaを手にしてからであるのは間違いない。夜の街を撮るようになったのもこのIIIaからだし、フィルムをいろいろと試行錯誤し始めたのもIIIaで昼夜いろんなシーンを混ぜて撮るようになったからだ。
今でこそM3もデジタルライカM-P(typ240 )も街撮りスナップに連れ出すことは少なくないけど、それもIIIaでライカが街撮りスナップに適していると気がついて、IIIaの延長線上というかバリエーション的に撮っているところがどこかある。つまりIIIaにない性能という意味で、静かに撮りたい時やファインダーをある程度眺めて撮りたい時はM3、少し量を撮りたかったり明暗のあるシーンで撮りたい時はM-P、そんな具合だ。
やはりベストバランスは、IIIaなんだよね。それはもう、このコンパクトさと手に持った時の自由さのようなものに尽きる。IIIaはバルナック型の中でもひときわ小さいボディ。これに沈胴式のElmar 50/3.5を装着した時の持ち歩きやすさは、M3もM型デジタルも敵わない。カメラを常に手に持って歩くのなら別だけど、なにげに鞄の中に入れて常に持ち歩き、撮りたいシーンに遭遇したら片手感覚でサクッと撮る、そんな芸当はいかにもバルナック型ライカの真骨頂だ。
いわゆるコンパクトカメラももちろんスナップシューターとしては優秀たけど、僕の場合だとRollei35やKonica C35で撮る時とLeica IIIaで撮る時とは多少心持ちが違う。携帯性重視ではなくて、あくまで本格的シューティング重視で撮る感覚がIIIaならしっかり堪能できる気がするんだ。街撮りスナップを軽快に楽しみたいけど、M3まで大きく重くなるとちょっと…というひとは、ぜひともバルナック型ライカを手にしてみてほしい。実際に手に持つとこれほど洗練さを感じるクラシックカメラは他にない。その手触りが、はやく街へ連れ出してみたいと強烈に思わせる。IIIaといったバルナックライカは、生粋のスナップライカなんだ。
そう考えると、このIIIaまでのライカの開発に携わったオスカー・バルナックというひとは、単にカメラ製造会社の開発者だったわけじゃなく、ひとりのカメラ愛好家としてとてもリアルに理想的カメラのあり方、使い方、日々持ち歩く時の心地よさを徹底的にイメージして、このカメラにそれらを凝縮して落とし込んだんだろうなというのが強く伝わってくる。その域までいくと、もはやフィルムカットの手間なんていうのは大した問題じゃない。常に肌身離さず持っていたいと思わせる絶妙の大きさとフォルムこそが、このカメラの最高性能であり存在意義なんだということ。そこまで突き詰められたカメラが、後発で出てきたんじゃなくて、35mmフィルムカメラの第一号機としてこの世に登場したことには正直、驚きを隠せない。その後に出てきたカメラたちが未だにバルナック型に敵わないということでもあるんだからね、スナップライカとしてはね。
★今日の新品/中古情報をチェック!